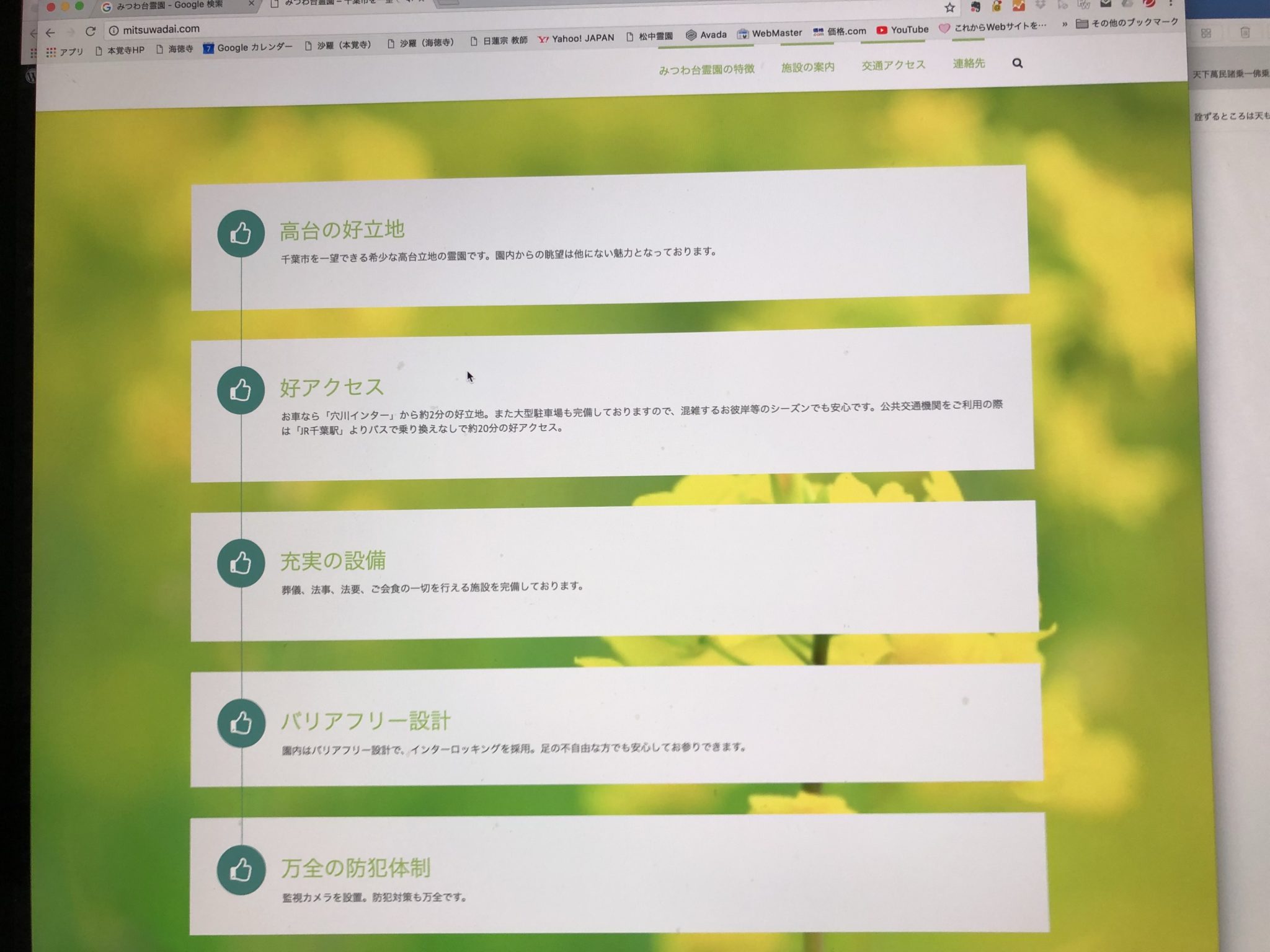はじめに
まもなく弟子が日蓮宗の僧侶となるべく信行道場に入ります。その準備をしている際に、昔僧侶の方々が学んだ檀林のことをふと思い出しました。長年京都の松ヶ崎に住んでいたので、松ヶ崎檀林については知っていました。しかし、他の檀林は行ったことないなと思うようになりました。そこで、関西の檀林について調べ、お参りに行ってきました。
今回は関西六檀林のうち、鶏冠井檀林、東山檀林、山科檀林を巡ってみました。
檀林とは
檀林とは、かつて僧侶が集まって学んだ教育機関のことです。僧侶が集まって学ぶ様子を、栴檀の林になぞらえた呼称です。日蓮宗では江戸時代から明治にかけて開設されました。
一致派(法華経の本門・迹門の教義が一致すると主張する門流)では、関東八檀林と関西六檀林が、一方、勝劣派(法華経の本門・迹門とでは優劣があると主張する門流)では、六檀林が知られており、所在地は千葉県が圧倒的に多いです。
- 小西檀林(正法寺) 千葉県大網白里市
- 飯高檀林(飯高寺) 千葉県匝瑳市
- 中村檀林(日本寺) 千葉県香取郡多古町
- 西谷檀林(久遠寺) 山梨県南巨摩郡身延町
- 松崎檀林(顕実寺)千葉県香取郡多古町
- 玉造檀林(蓮華寺)千葉県香取郡多古町
- 三昧堂檀林(久昌寺)茨城県常陸太田市
- 南谷檀林(照栄院) 東京都大田区
- 松ヶ崎檀林(涌泉寺) 京都市左京区松ヶ崎
- 求法院檀林(本圀寺) 京都市山科区御陵
- 東山檀林(善正寺) 京都市左京区岡崎
- 鷹ヶ峯檀林(常照寺) 京都市北区鷹峯
- 山科檀林(護国寺) 京都市山科区竹鼻
- 鶏冠井檀林(北真経寺) 京都市向日市鶏冠井町
- 小栗栖檀林(本経寺) 京都市伏見区
- 三沢檀林(豊顕寺)神奈川県横浜市神奈川区
- 宮谷檀林(本国寺) 千葉県大網白里市
- 細草檀林(遠霑寺)千葉県大網白里市
- 大沼田檀林(妙経寺) 千葉県東金市
- 大亀谷檀林(隆閑寺) 京都市伏見区
参考資料:日蓮宗の檀林寺院
鶏冠井檀林真経寺(南真経寺・北真経寺)
北真経寺は京都市の南隣・向日市にあります。四条で梅田行きの阪急電車に乗り、電車に揺られること15分程。途中思い出の西京極球場のグラウンドが目に入り、30年前近くに大学野球で試合したことを思い出しました。


Googleマップにて事前に場所を調べると、西向日駅から徒歩5分。かつては一つのお寺だったのが、現在では北真経寺と南真経寺の2つに分かれており、場所は線路を挟んで東と西。そんなざっくりとした情報のみでとりあえず歩いて見ました。
石塔寺
歩いてすぐにお寺が目に入りました。お題目が書かれてあり、北真経寺か南真経寺のどちらかのお寺かと思って入ってみると、こちらは石塔寺という別のお寺でした。こちらのお寺は現在では日蓮宗ではなく、本化日蓮宗という単立の寺院でした。




当寺は、明治10年(1877)代にまとめられた「乙訓郡寺院明細帳」によると、鎌倉時代の末の延慶3年(1310)3月8日に、開山日像上人が現在の場所に題目石塔を建立し、文明年中(1469〜87)にこの石塔の傍らに本堂を建立して寺院としたのが創まりと伝えられています。元和年中(1615〜24)に不受不施派の寺院として幕府に願いを出しましたが、寛文6年(1666)に不受不施派禁制後は、妙顕寺派に属しました。その後、同寛文年間には、独立本山に成長し、その末寺は近畿一円に総数33ケ寺に達していました。
明治9年(1876)に鶏冠井村にあった興隆寺を合併吸収し、翌年に本堂・庫裏・座敷・小座敷・塔堂・七面堂・妙見堂・鐘楼・門などを整備しました。現在は、本化日蓮宗本山の単立寺院であります。
周辺には、本寺にちなんだ「御塔屋敷」「御塔下」「御塔道」などの地名が残っており、往時の伽藍の壮大さをしのばせてくれます。
また、この地一帯は、長岡京(784〜794)の時代には、京都の中心部に位置し、造宮長官の藤原種継の暗殺場としても知られています。平安時代に、土佐国から帰路についた紀貫之が京に入る前に休息した「島坂」も当寺周辺だと伝えられています。
鎌倉時代以降は、寺の前を通る西国街道を行き交う人々で本寺周辺は賑わいを見せ、豊臣秀吉や明智光秀など歴史上の人物が次々通ったと言われています。
南真経寺
石塔寺から徒歩数分で南真経寺に到着しました。中学校の目の前で自動車が行き来する通りに面しているのでわかりやすかったです。真っ先にお題目が書かれた石塔が目に止まりました。

日蓮宗関西最初弘教之地と書かれております。日蓮聖人から京都弘通を託された日像上人が、関西ではこの地で最初に教えを弘めたという当時の状況を想像するととても感慨深いです。現在では京都だけでなく関西にも数多くの日蓮宗寺院がありますが、この鶏冠井という地が関西最初の布教場所となります。






当寺の創建は、寺伝では鎌倉時代末の徳治2(1307)年とされています。
御開山日像上人は、宗祖日蓮聖人の帝都に日蓮宗布教せよとの遺命を受け鎌倉時代末期に上洛されたが、他宗派の迫害をうけて、しばしば京都から追放され、これを三黜三赦(さんちつさんしゃ・三度追放されその度に赦される)といい、徳治2(1307)年頃、乙訓郡山崎付近にとどまって布教活動を行っていました。
当時、鶏冠井には、真言寺という真言宗の寺院がありましたが、住僧実賢(じっけん)は日像上人の教化によって日蓮宗に改宗し、寺名も真経寺と改めました。(真言寺の真と、日像上人の幼名経一丸の経をとられた)真経寺は、関西における最初の寺院となり、以後日像上人の布教活動の拠点となりました。現在向日神社参道前の左に日像上人が石に座して説法された説法石が祭られています。
真経寺は、はじめは、一寺でありましたが、江戸時代の承応3(1654)年に、南北の2つに分かれ北真経寺は檀林(仏教の学問所)、南真経寺は鶏冠井村民の信仰の場となりました。法華経の信仰を現した当時の鶏冠井題目踊は京都府無形文化財に指定され踊り継がれています。
明治時代の初めの頃に整理された台帳には、山門正面にある開山堂が寛永11(1634)年に、本堂が正徳4(1714)年、鐘楼は元禄12(1699)年の建立と記されています。また「真経寺」の額は本阿弥光悦により書かれたものです。
寺宝は、御霊宝箱に納められ南北真経寺の間で管理されています。この中の尊性法親王消息翻摺法華経(開結10巻)は、国の重要文化財に指定されています。

日像上人の京都での布教は最初からうまくいったわけでなく、洛外へと追い出されていたことを初めて知りました。迫害があったが故に、この鶏冠井の地で布教を行い、そこから再度洛中での布教活動に結びつくことになります。
北真経寺
かつて真経寺という1つのお寺だから、きっと南真経寺の近くにあるのだろうと予想して、地図も見ずに歩きました。しかし、ずっと1時間程歩いても北真経寺の場所がわからず、再び西向日駅に戻ってしまいました。
途中、長岡宮築地跡の看板が目に止まり、この辺りが昔の長岡京であることを知りました。向日市の隣の長岡京市には自動車免許の更新で何度か行っており、奈良・平城京から、長岡京に都が移り、その後京都の平安京へと首都が移動したものと思っていました。が、実際には向日市に日本の首都だったとは驚きです。
1時間経ってようやくGoogleマップを開きました。すると、南真経寺からそれほど遠くない所に北真経寺があるとの情報が。ただし、南真経寺と異なり北真経寺は通りから少し入った所に位置していました。
北真経寺、南真経寺となっていますが、地図上は阪急電車の線路を挟んで東が北真経寺、西が南真経寺かなと思います。








本寺は鶏冠井山と号する日蓮宗の寺院です。南真経寺とはもと1寺であり、江戸時代前期の承応3年幕府の佛教統制によって分立し今に至る。鎌倉時代末期永仁2年(1294)に京都に入った日像聖人は活発に日蓮の教えを説き、次第に有力な町衆を信徒に加え洛中に妙顕寺を建立した。後醍醐天皇より独立した一宗として公認されるに至る。
しかし、それまでの40年の間には、比叡山を中心とする他宗からの迫害を受け2度3度と洛中を追放された。西国街道沿いの向日神社や鶏冠井の集落に日像聖人の足跡がしるされたのはこの追放の時期のことである。其頃鶏冠井に密教系の真言寺があり住持を実賢律師といった。
徳治2年(1307)頃、乙訓郡山崎付近にとどまった日像はさかんに布教活動を行っていました。或時向日明神に法華弘通の祈願をされた折、境内に野宿し一夜を明したるところ、白髪の明神現れ夢の御告げを頂かれた。汝此地に法華経を弘めよ、と。これを縁として日像は西ノ岡に於いて布教することになります。鶏冠井の集落に於いては特に日像の教化に信伏する村民が多く、日像は住持の実賢と法論をたたかわすこととなり三昼夜に亘って法論の末、ついに実賢は日像に帰依して弟子となって、真言寺も寺号を真経寺と改めることとなりました。こうして真経寺は関西に於ける日蓮宗最初の寺院となり、以後日像の布教活動の拠点の1つになったのです。江戸時代、前期に南北両真経寺に分かれた時、北真経寺は檀林が設けられ多くの僧が学び教典の収集や教義書の出版などをしていました。明治初年には檀林は廃されて本堂周辺の5つの大きな建物も取壊されました。そして今日に到っています。尊性法親王消息翻摺法華経10巻は重要文化財、日像秘要集3巻、南北共有



東山檀林・善正寺
東山檀林であった善正寺は京都大学すぐそばでした。野球部の練習後によく通っていた末広食堂からほどない距離でした。


しかし、こちらの善正寺も地図なしでなんとなく行くには難しく、気がつけば黒谷の浄土宗大本山金戒光明寺に。吉田山荘の方にも向かって見ましたが見当たらず、途方にくれること40分程。最終手段のGoogleマップを用いて調べたら、小学校の隣に善正寺はありました。


山科檀林護国寺
山科檀林があった護国寺は、三条通に面した所です。山科駅からも近く歩いて行くことができます。かつて京都に住んでいた頃に「日蓮宗護国寺」という看板が目に入っていたので、だいたいの場所は把握しておりました。そのため、今回はGoogleマップなしで行くことができました。

護国寺さんは若住職さんがSNSやホームページなどで情報を発信しております。とてもわかり易く参考になると思います。




当山は山号を了光山。寺号を護国寺といい、1643(寛永20)年3月に法性院日勇上人によって開創された日蓮宗のお寺である。また明治5年までの230年間、僧侶の修行道場である山科檀林として栄え、関西六檀林のひとつであった。
歴代の住職は、化主(けしゅ)と呼ばれ学徳全てが備わっていないとなれず、京都東山にある本山妙傳寺の猊座をはじめ、総本山である身延山久遠寺の法主の猊座に何人もすすんでいる。後水尾天皇の皇后、東福門院は開山上人に自ら縫ったと伝わる菊の御紋・金袈裟を寄進。この袈裟は日蓮宗初の金紋袈裟であり、以後、山科檀林の歴代化主の歴代化主は着衣が許される事となる。
当山にお祀りする妙見菩薩は泥棒の詫び証文が伝わっており、盗難除けの守護神として崇信され、弁財天女は開山上人の霊夢により、火伏せの誓いがあって火難避けの地主神、また七面大明神は法華経信仰者の守護龍神として信仰をあつめた。
現存する総門は伏見宮家、紀州徳川家の寄進。『栴檀林』の額は深草元政上人の墨蹟である。

参考サイト
檀林の情報をインターネットで検索していてふと目に止まった論文がこちらです。
木村中一「近世日蓮教団の檀林における修学内容についての一考察」『印度學佛教學研究』第65巻第2号(平成29年3月)、pp.187-193.
檀林での修学内容は主に天台学が中心で、日蓮聖人の御遺文の研鑽が先送りにされたという話です。
その背景には
天文法華乱→安土宗論→方広寺大仏殿千僧供養会→慶長法難
という一連の法難が日蓮宗の布教方針に大きく影響を与え、檀林の教育内容にも反映されているとのことでした。先の論文からの引用を紹介いたします。
以上、日蓮教団の一大変革期となった室町末期より江戸時代の代表的な事件を確認した。これからもわかるように、天文法華の乱以前には一大興隆をみせた日蓮教団も、他宗からの迫害、また安土宗論に代表される為政者からの弾圧などにより、以前までのような宗論対論を中心とする強義折伏伝道活動は封じられ、さらに日蓮以来の純正不受不施を標榜することが難しくなった。これらの事件は日蓮教団の存亡に関わり、一大決断をなさねばならない事項であった。つまり今までの日蓮教学を表に出す伝道活動では更なる教団弾圧を生むことは火を見るよりも明らかで、そのためにも教学研鑽に変化を図らねばならなかったのである。これこそが当時の日蓮教団を見舞った、先の「時代の潮流」に他ならないのである。